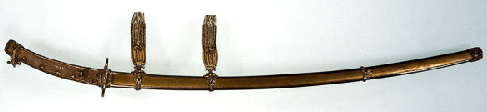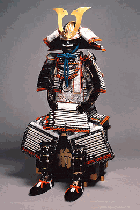鐔の歴史
1. 鐔の発生

- [ 倒卵形鍍金透鐔 ]
古墳時代
鐔の歴史は、古墳時代の環頭太刀 (かんとうたち) や頭椎太刀 (かぶつちたち) に着けられていた倒卵形鍔から始まっている。
順次、時代を追って、飾剣、毛抜形太刀、兵庫鎖太刀、蛭巻太刀、黒漆太刀、革包太刀、糸巻太刀などに刀装され、形を変化させてきた。
しかし、今ここでは、それらの鍔の歴史は省略し、我々が単に鐔と呼んで鑑賞している打刀用の鐔についての歴史を述べることとする。
打刀とは、太刀とは逆に、刃を上にして腰に差す刀のことで、南北朝期に出現した。それ以前の戦においては、騎馬による平地戦がほとんどだったが、この頃から、徒歩による山岳戦などが増え、その結果、武士たちが身に着ける武具は、迅速な行動がとれ実用性のあるものへと変わっていった。
すなわち甲冑では、鎌倉時代までの大鎧に変わり、胴丸・腹巻など体に密着して活動に簡便なものが流行し、刀剣においては、腰に佩いて浮動する太刀から腰帯に直接差して揺れ動くことの少ない打刀を使用するようになった。
打刀は腰に差すものであるから、太刀のように鞘に多くの金具がつかず、ただの塗鞘で栗形と返角 (かえりづの) だけがつく簡素なものである。柄は鮫着に組糸または染革巻となり、そこに目貫が巻き込まれた。
そして、応仁の乱 (1467 - 1477) を経て戦国時代ともなると、打刀が一般的なものとなった。

- [ 兵庫鎖太刀 ]
鎌倉時代

- [ 大鎧 ] (模造)
足利尊氏着用
2. 鍔専門工の出現

- [ 刀匠鐔 ]
室町時代前期
現在我々が一個の独立した美術品として鑑賞している鍔は、打刀につけられていたものである。
室町期において、打刀は太刀に代わって多く用いられるようになった。打刀に装着する鍔においては、それを専門に製作する鍔専門工が初期の頃から存在したとは考えにくく、刀を製作する刀匠が需要に応じて製作した鍔 (刀匠鍔)
、あるいは甲冑工などの武具を製作する者が余技として製作した鍔 (甲冑師鍔) などが主に打刀に取り付けられていた。これら初期の鍔は、文様がまったく無い板鍔か、簡素な小透かしが施されたのみのものが多い。
これらの鍔のうちでも特に甲冑師鍔は、この時代の趣を十分に感じさせてくれるものである。
甲冑師鍔は、鉄の鍛えがよく、薄板で大ぶりなのが特徴で、耳は角耳・打返し耳・土手耳であることが多い。
そして、小さく施された透かしの文様や文字からは、これを刀に装着して戦場へ向かった者たちの信仰・思想・心映えを読み取ることができ、その時代の息吹を十分に感じさせてくれるのである。

- [ 応仁鐔 ]
室町時代後期、推定
このようにして鍔を専門に作る職工が出現したわけだが、それら鍔専門工によって作られた最初のものに、応仁鍔、あるいは鎌倉鍔がある。
応仁鍔とは、応仁の乱のころに創始されたと推察されることから後世の人にそう呼ばれる鍔のことで、その特徴は、甲冑師鍔に似て薄い鉄板で、装飾には真鍮の点象嵌や線象嵌を用い、切羽台や櫃穴のまわりを象嵌で縁どりしてあるところである。
また、応仁鍔より少し時代が下がり、より象嵌の技術が進歩しているものに平安城式真鍮象嵌鍔がある。平安城式真鍮象嵌鍔は、家紋や唐草などの文様が鍔全面に真鍮象嵌され、応仁鍔より精巧で装飾性が高いものとなっている。
鎌倉鍔とは、その作風が木彫りの鎌倉彫に似ていることから後世の人が名付けた鍔のことで、やはり薄手の鉄地に、塔や橋あるいは中国風の楼閣山水などを鋤出し彫りで表現しているところに特徴があり、さらに透かしを加えたものもある。
こうして、室町時代後期に登場した鍔専門工によって、鍔に透かしや象嵌などの装飾を加えることに重きがおかれるようになり、それは刀匠鍔や甲冑師鍔などの衰微を招く結果となった。
3. 芸術性の加味と流派の多様化

- [ 葡萄胡蝶文鐔 ]
銘・埋忠明寿
江戸時代初期 (重要文化財)
さらに戦国時代・安土桃山時代ともなると、鍔に装飾性を持たせようとする流れは加速し、鍔に用いる図柄や構図、あるいは、地金や象嵌に用いる金属なども多様化した。
例えば、それまでは塔・鎌・鋤・草花などを簡単に透かしにするなど図案風のものしか存在しなかった鍔だが、金家は鍔に絵画的な美を加えて絵風鍔の祖と呼ばれた。
また、金家と同じ頃、京都では埋忠明寿 (1556-1631) が出て、金・銀・赤銅・素銅などの色金を巧みに平象嵌・色絵して、写実的な鍔を多く生み出した。
一方では、足利義政の側近として仕えた後藤祐乗 (1440-1512) を祖とする後藤家が、美濃金工の様式をさらに格調高いものとした後藤風を確立し、装剣金具の様式上の基本を作り上げた。
ちなみに、後藤家は、彫金の面で優れていたばかりでなく、貨幣の管理という財務面でも力を発揮した為、足利・織田・豊臣・徳川と各時代の権力者に重用され、明治の世になるまで祐乗以下17代繁栄し、またその支流も大いに栄えた。
4. 刀装具様式の画一化
安土桃山時代が過ぎ、江戸に幕府が開かれると、徳川氏を頂点とする強力な幕藩体制が構築され、文化の中心も自然と京・大阪から江戸に移っていった。
金工の世界も、幕府御用となった後藤家・吉岡因幡介家・平田家などが興隆することとなる。
このうち、平田家は少々特異で、始祖・道仁が朝鮮役の際に朝鮮人から教わった、あるいは、長崎でオランダ人から習得したとも言われる七宝の技術を一子相伝で伝え、色鮮やかな刀装具を製作している。
大坂の陣が終わった頃こそは色濃く残っていた戦国の気風であるが、江戸幕府が様々な法令を発布して制度化するにつれ、そのような荒々しい気風も廃れていった。
幕府は、1615年に武家諸法度を発布し、後には参勤交代制度や大船建造禁止令などが加えられた。
1645年には、「大小刀の寸法および頭髪髴毛の制」が定められ、刀は2尺9寸まで、脇差は1尺8寸まで、大鍔・大角鍔、朱鞘あるいは黄鞘は禁止などとされた。
また、大名・旗本が登城する際の大小拵の様式も定められ、鞘は黒朧塗、柄は白鮫着で黒糸巻、頭は角、三所物は赤銅魚子地、鍔は赤銅磨地あるいは魚子地と限られていた。
このように、刀装に制約が加えられたので、鍔などの刀装具の様式も画一化が進むこととなった。
以上のような経緯で様式の自由度が失われた反面、決められた様式内での技術的な工夫発達が見られるようになり、これが、様々な技巧を駆使する名工を輩出することとなる。
5. 技術の競演
大坂の陣・島原の乱を経て、戦乱の世が昔話となる時代になると、やがて世相は豪奢に流れ、刀剣も、実用武器としてより、武士であることの象徴という意味合いが大きくなってきた。
このような泰平の生んだ世相は、鍔の製作においても、見た目がより重要となり、技術面の顕著な進歩を促した。
この時代、刀匠の数はめっきりと減り、代わって、町彫と呼ばれる金工から多くの名工が出現した。
この期に製作された鍔は全体的に、技術的な進歩は認められるが、技術に走るばかりに、ややもすると趣きに欠けるものも多く見られる。
しかしながら、この元禄以降幕末に至るまでの時期が、鍔の歴史において最も華やかな時代であり、多くの鍔工たちが覇を競い合った為、優れた作品も数多い。
横谷宗珉は、後藤の家彫を基礎に、絵画の才能を活かした下絵、片切彫の工法などをもって新たに横谷風を編み出した。
宗珉の弟子たちには、子の宗与・柳川・大森・岩本・石黒・古川・稲川・桂・佐野・菊池・菊岡などがおり、それぞれが一派を形成するほど横谷流は興隆をみた。
江戸において横谷と並び称される流派は奈良派である。
宗珉とほぼ活躍期を同じくして、奈良三作と呼ばれる3人、奈良利寿・杉浦乗意・土屋安親、あるいはそれに次ぐ存在の濱野政隋が現れ、刀装具の芸術性を大いに高めた。
一方、京都においては、梅忠派や正阿弥派が残っていたが抜群の技量を持つ金工を輩出しなかった。
むしろ両派以外のものに注目すべき金工がおり、一宮長常 (1722-1786) は、越前国敦賀の出身で、京都へ上り保井高長家に入門し、のち独立した。
作風は、高彫色絵のものと片切彫平象嵌のものが多く、同時期の江戸の宗珉と並び称されるほどであった。
その他、鉄地の名品鍔を多く製作した"鉄元堂"岡本正楽、絵画を岸駒に習い、また円山派などの筆法を取り入れ下絵に活かした大月光興が、長常と合わせて、京都の三傑と呼ばれる。
地方においては、まず会津藩と長州藩が、鍔工と作品数の多いことで知られている。
長州では、藩の財源とするために鍔の生産が奨励されていた。
会津においては正阿弥一派が有名であり、長州においては様々な流派が興隆したが、各家の作風は大同小異であるとも言える。
江州 (近江国) では、鉄地丸形に武者や仙人などの人物を肉彫り象嵌色絵で配した、藻柄子宗典製の鍔が大変な人気を博した。
また、越前国の記内・赤尾の両派、肥後金工の各派、長崎の若芝および南蛮鍔、水戸の金工諸派などが、それぞれの特長から、全国的な人気を集めた。